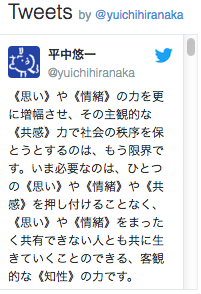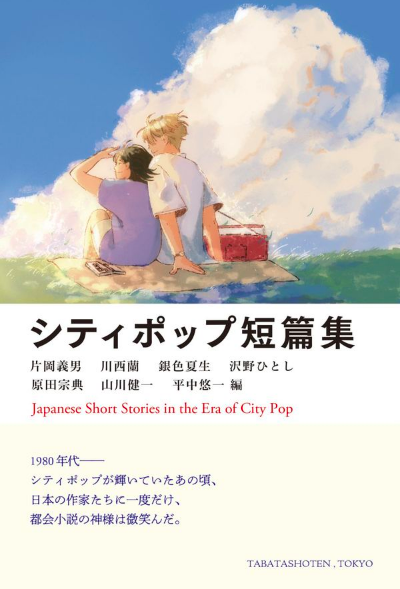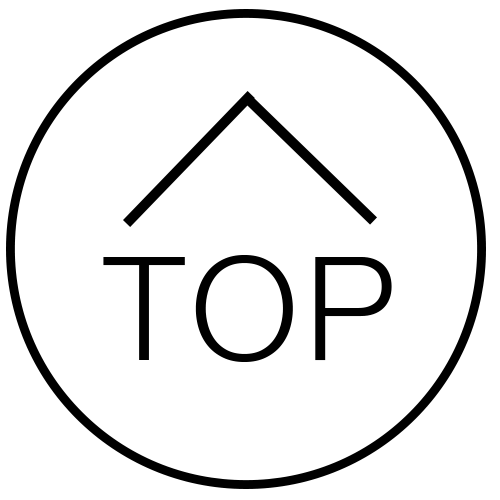3 Au retour de Paris…
*フランス的*ってなんなんだ?
 渡仏後にラジオで聴いて、はじめて、これはいい、と思ったミュンシュ指揮の『幻想』。
渡仏後にラジオで聴いて、はじめて、これはいい、と思ったミュンシュ指揮の『幻想』。
なんでも聴けるはずの、しかも本国フランス、パリ市の図書館で、その演奏のディスクがどうも見つからず、僕の中でマボロシ化してしまっていた、そのわけは、日本に帰って日本のamazonなどをみるとすぐに判った:
まず、まったく思いつきもしなかったが、なんと、それはフランスの国立視聴覚研究所の*秘蔵*音源を入手し、新たに製作された日本国内プレス盤、なのだった。パリ市の図書館の、どこかにはあったかもしれないが、どこにでも常備されているようなディスクではなかった;
次に混乱させられた理由に、これが例の、僕がどうもうまく馴染めなかった*大定番の名演*と同じ1967年に行われた、ホール収録、ということがあった。つまり、まず17区のヴァグラムというホールでその大定番の録音をセッションで行ってから、満を持し、8区のテアトル・デ・シャンゼリゼでのコンサートに臨んだ、その際のライヴ音源、という時系列、らしい。そしてこれこそが、*歴史的な*パリ管の旗揚げ、イノギュレーション公演だった。
…さて。ここで、まず、子どもの頃には思わなかったが、いまなら、《待てよ…》と思うことがある(笑)
日本のクラシック・ファンには、ほぼ謎に近い*出身国*信仰があることは以前にも書いたが(こちら)実際には、ヨーロッパ人は、たとえフランス人といってもおばあさんはスペイン人とか、イタリア人とか、そういうことはザラにある。交通だけでなく戦争の歴史もダイナミックで、現在のヨーロッパの国境線で、過去の国やその文化を考えるのは、相当いい加減な話になるしかない。つまり、フランスの作曲家、フランス人の指揮者、フランス人のオーケストラ、という考え方自体が、そもそも、かなり当てにはならない。
さらにここには、そのパリ管の*歴史的な旗揚げ*という問題がある。
パリ管というのだからもちろんフランスの象徴=*フランス的*…と子どもの頃は無反省に思っていたが、実はこのパリ管というのは、パリ音楽院のオケを母体としながらも、
それまでのフランス的なドメスティクなオーケストラでなく、
世界に通用する、音楽スタイルも、個々のパートの音色・奏法も、インターナショナルなオーケストラを作ろうという政府の肝入りで、
長年アメリカなど国外で活躍したミュンシュが、もう高齢(事実死の直前)であったにも関わらず、そのインターナショナルな手腕を買われ、シェフに請われた。
つまり、フランスでは、*パリ管の誕生*=エコール・フランセーズ(フランスのオーケストラ独自の伝統)の終焉、というのが、常識、といえる。
そのミュンシュ、パリ管の録音を、
《ベルリオーズはフランスの作曲家なので、フランスの指揮者とフランスのオケで、*フランス的*な演奏を味わうべし》
というところで持ってくるのは、いろんな意味で、ちょっとずれてる(笑)
ミュンシュやフランス政府の意図を完全に無視しているだけでなく、すぐ次に続くとおり演奏の実質も無視しており;)
フランスの音楽ファンから見ると、ほとんど*誤解*に近い(笑)
…まぁ、所詮フランスのクラシック局で聞いた知識の受け売りだが;)さらに、ラジオで聞き知った知識といえば、冒頭にも書いた、この*フランス的*という問題がある。
もちろんフランスにも、つまりフランスのクラシック・ファンにも、*所謂*、括弧つきの、よくいわれる、俗にいう、*フランス的*なサウンド、というものはある。例えば透明感だの、浮遊感だの、軽やかさだの…云々かんぬん。
しかし例えばラジオフランスの音楽局のDJなど、僕がよく聴く限りだいたいが、音大で音楽学をやっていたり、作曲をやっていたり、楽器が弾けない、譜面が読めない、という人はまぁ、いない。
(つまり、フランスだと、音大で音楽を勉強すると、音楽専攻として、ラジオという就職先もある、ということ。ひるがえって日本のFMに、音大を出た人がどの程度採用されているのだろう?)
そういう人たちがフランス的、というときその意味は、そういう曖昧な雰囲気の話ではなく、むしろ具体的な楽器の奏法であったり、音色であったり、ピンポイントで、ここの音が…という形である場合もふつうに多く、何年かラジオを聴いてると、オーヴァータイムで、だんだんこういうのがフランス的なんだ。。とはっきりしてくる。
その耳で、ミュンシュ、パリ管の『幻想』を聴けば、もちろんこれは、まったく*フランス的な*演奏ではない。いうまでもないだろう。だって、フランス的じゃないオーケストラ、というのが、そもそものパリ管の出発点、アイデンティティだったわけだから(笑)
世界に通用するインターナショナルなオーケストラを作ってくれと本国フランス政府から招請された外国暮らしの長いミュンシュが、そのお披露目録音と、光の都=パリもど真ん中、テアトル・デ・シャンゼリゼの初舞台に、どうだ、これでもか、こんなに違って、新しいぞ!と目にもの見せようとしたことは、作中架空人物の*内面*でさえ*推察*させる驚異の国語教育で育成された日本人の想像力にとって、マークシートなら軽く一択、ではなかろうか。。;)
(シャトレ座などの方が地理的にはぜんぜん真ん中では…等のテクニックな点は、ここではこの際問いません・笑)
僕が子どもの頃のレコード評論家の皆さんは、もはや全員鬼籍に入ってる気がするので(多分;)この際遠慮なく、密かに思うに(笑)*フランス的*というんなら、具体的にどういうことを、どこを指していってるのか。
もしそれが明確にいえないとしたら、そんなもん、もう、デタラメな話、与太話、でしかないだろう。
とこう書くと、当然、非常に厄介な事態に書いた本人を巻き込むのは自明、である。
じゃあ、どこがその、フランスで一般的にいわれるフランス的な音なんだよ?
具体的に、明確に、示さないなら/示せないなら、デタラメ、与太話なんだろ??
というチャレンジが、誰からでもなく、当然書いた自分によって発動してしまってるからだ。。;)
…というわけで、はい、すみません。ここでポケットスコアを出してくる、という暴挙に出ました(笑)これです。
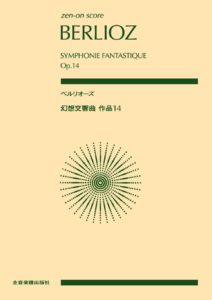 オーケストラのスコアというのは、クラシックファン以外の人は買ったことはもちろん、見たこともないかもと思いますが(笑)ベルリオーズの譜面は見た目にも、たとえばベートーヴェンの楽譜とはまったく違う。見ているだけでも、コール・ド・バレエ、音符がダンスのようで、楽しい(笑)
オーケストラのスコアというのは、クラシックファン以外の人は買ったことはもちろん、見たこともないかもと思いますが(笑)ベルリオーズの譜面は見た目にも、たとえばベートーヴェンの楽譜とはまったく違う。見ているだけでも、コール・ド・バレエ、音符がダンスのようで、楽しい(笑)
さて、では、問題の、フランス的な演奏の実例だが。。
もちろん、ミュンシュ、パリ管の録音では、それは説明できない。つまり、もちろんないものはない、ただ単純にないわけで(笑)ほらほら、ここにないでしょ、といくらいったところで、何がないのか判らない、そしてその*ないもの*が、フランス的なわけだから。。;)
(ミステリなどでもよくいわれる不在証明…結局、存在しない、ということは証明不可能で、証明できるのはただどこかに存在することのみ、それがアリバイ…という話にちょっと通じますか;)
フランス的な演奏であることがよく判り、しかも演奏自体もいいもの。。ということで、何かないかと探してみたところ、例えば、これ。これはどうでしょうか。
問題の、パリ管の前身、パリ音楽院のオーケストラをクリュイタンス(ベルギー生まれです、すみません;)が振った東京公演の『幻想』。
 …このクリュイタンス盤で、例えば1楽章、スコアでいうなら24小節目からのアンサンブルを聴いてみてください。さらに50小節目からのホルン・ソロ、240小節目からの白玉!
…このクリュイタンス盤で、例えば1楽章、スコアでいうなら24小節目からのアンサンブルを聴いてみてください。さらに50小節目からのホルン・ソロ、240小節目からの白玉!
あるいは2楽章、120小節目からのフルート、オーボエのユニゾン、163小節目からの木・金管アンサンブル。
3楽章は緩徐楽章で、まぁ、のっけからかなり判りやすいが(笑)さらに36小節目〜や、119小節目〜のクラリネット。そしてもちろん、終盤、175小節目〜のイングリッシュ・ホルン…。こういうのは、本当にフランス的な音色、といえます。
こういった部分の特徴をどうことばで表現するかは、何度もラジオで聴いてますが、まぁ、それは結局フランス語なので(笑)具体的にはこの音そのもので、聴いて、理解してもらうのが何より、でしょう…。
他にも何かいい例はないかと何枚か多少聴いてはみたが…フランス的な音色・奏法をいまに伝える録音で、演奏も録音も…ということで、お奨めできるディスクというと、僕が気づいたところでは、このクリュイタンス盤以外にありませんでした。残念です。
…かつて日本で常に「*フランス的*なサウンド」と評されていた1枚、今や#MeTooで干され晩節を汚しまくっているマエストロたちの一人(笑)デュトワ指揮モンレアル響は、さすがに確かにフランス的なサウンドの特徴を示しているが、しかしこれは、演奏自体に魅力がない(笑)
 昨年、ベルリオーズ・イヤーの『幻想』新録としては、フランソワ-グザヴィエ・ロト&レ・シエクルの再録 [mp3| cd]が注目盤の最右翼だったろうが、作曲された当時の演奏の再現を第一義とするピリオド演奏派のロトは、フランスで普通いわれるフランス的な奏法、音色を一切許さない。
昨年、ベルリオーズ・イヤーの『幻想』新録としては、フランソワ-グザヴィエ・ロト&レ・シエクルの再録 [mp3| cd]が注目盤の最右翼だったろうが、作曲された当時の演奏の再現を第一義とするピリオド演奏派のロトは、フランスで普通いわれるフランス的な奏法、音色を一切許さない。
これはつまり、フランス的な奏法、演奏といったところで、実際に耳にできるのはレコード誕生以降のものであり、リアルに話として聞けたのも、普通に祖父の世代までだから、
ロトの立場は20世紀後半に失われた“エコール・フランセーズ”の奏法というもの自体が、ベルリオーズの頃には存在しなかった、後世の悪癖である、というものらしい(笑)
このロト新盤に関しては、ベルリオーズ演奏のために特別に鋳造された鐘を使っている、ということがラジオ・フランスでも話題にされていた。
 クロッシュのピッチというなら、マルティノン指揮のl’Ortf(現フランス国立o)盤の当たり方もなかなかだったのではないか。。とはいえこのシャルマントな(ドッカン・ターボ的なコルネットはさておき;)演奏もまた、フランス的なサウンド、とはいえないだろう。。;)
クロッシュのピッチというなら、マルティノン指揮のl’Ortf(現フランス国立o)盤の当たり方もなかなかだったのではないか。。とはいえこのシャルマントな(ドッカン・ターボ的なコルネットはさておき;)演奏もまた、フランス的なサウンド、とはいえないだろう。。;)
ともかく、フランスのオーケストラ、ということにこだわる限り、他にはあまり目ぼしいタイトルが浮かばない。。
がしかし、この《フランスの作曲家なのだから、フランスのオケで、*フランス的*な演奏を楽しんでこそ本物!》という呪縛は、単に*誤解*に基づいているのみならず、
ミュンシュ『幻想』が理解できなかった、実は僕にとっての最大の要因だったかもしれない。。このあたり、さらに次パートでみていくが、
そんなことを考えるうち、ふと、高校時代のあるエピソードを思い出した。
そしてそれが、このポストを書いてみようと決意する、ひとつの契機ともなるのだった。。
(4 À l’ombre de jeunesse perdue…へ続く)