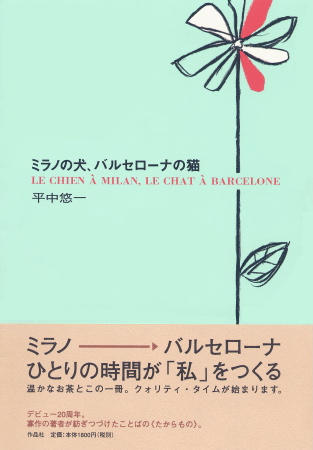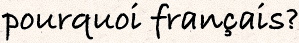
「・・・著者がフランス人だからに決まってんだろ!!」
何年か韓国語を勉強していると、やっぱりもう1度フランス語をやり直したくなってきた。
ところで、このファーイーストからは遠くはなれているのに、フランス語は、ふしぎなくらい韓国語に似ている、と僕は思う。
次にアクセントの問題だが、もし英語がイントネーションのわりに固定された言語であると定義できるなら――つまり英語として認識されるにはイントネーションが正しいことが必要だ、ということだ――フランス語と韓国語は、どちらもともにリズム・グループに支えられている言語である、ということがいえる。僕自身最初英語からフランス語を勉強しだしたとき、いちばんとまどったのがこのあたりで、たとえば英会話のテープを聴けば、例として読まれる英文は常に概ね同じイントネーションになる。ところがフランス語では、同じ文を3回読むと3回とも異なる抑揚で読まれている場合さえある。いったいどう読めばいいんだと途方に暮れたわけだが、じつは守られているのはイントネーションではなくリズム・グループで、何回読んでもリズム・グループはきちんと守られている。いいかえれば、フランス語をフランス語らしく、理解されやすく話すためにはリズム・グループを守らなくてはならない、ということになる。
「そりゃお前・・・」といって、ぐっと答えに詰まった僕は、結局こういい放った。
日本語と韓国語が似ている、というのはよくいわれることだ。文法構造も半ば同じであり、助詞も大半これはこれ、と置きかえることができるくらいで、またどちらのことばにも読みこそ違え、そもそも同じ漢語が大量に使われているため単語自体も概ね共通しているといっていい。ワードオーダーも大抵同一だし、表現の情緒も殆んどが理解し易い。逆にまったく違うのは発音で、韓国語の圧倒的な音のヴァリエイションは、識別する音数の極端に少ない日本語圏の者には、再現がかなり困難だ。
まず、どちらも中世以降、人工的に体系化された言語、というところがあり、ともにたいへん論理的だ。発音の規則などもそうで、よくフランス語はたとえば英語と比べて文法や発音など、規則を憶えることが多いからたいへんだ、といういい方をする人があるが、ほんとうは、英語はフランス語のように例外はこれとこれ、などといえるだけの規則もなく、つまり片っ端から丸暗記するしかないという、いわば、どちらかといえばでたらめな言語なんだ、といってもいい。まぁ、フランス人ならそういいかねない。英語のほうがフランス語より勉強しやすい、というのはただの思いこみ、といっていい部分も多いのではないだろうか。
そして、このこととも大きく関連しているのだが、フランス語と韓国語は、結果的に音としてとてもよく似て聴こえる部分がある。このあたりのことを、すごく簡単には、フランス語と韓国語にはどちらもリエゾンがある、というふうにまとめることもできるが、具体的にそれがどういう結果につながるか、というのは、そのひと言だけでは殆んど想像がつかないだろう。
昔、万葉集を韓国語の音で読み替えた本がベストセラーになったこともあるが、あれと同じ要領で読み替えられる部分がフランス語にもけっこうあるかもしれない。